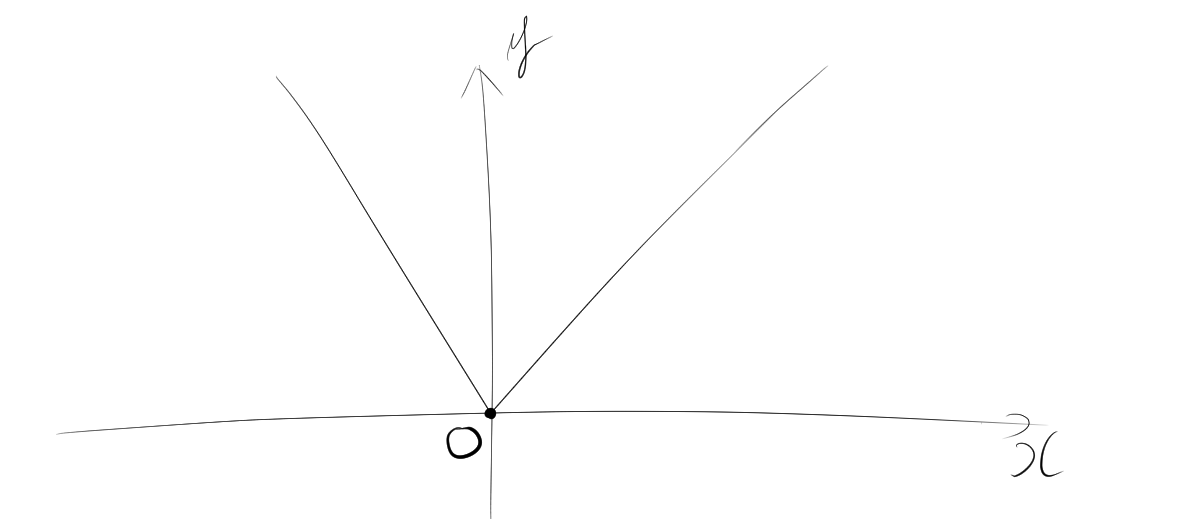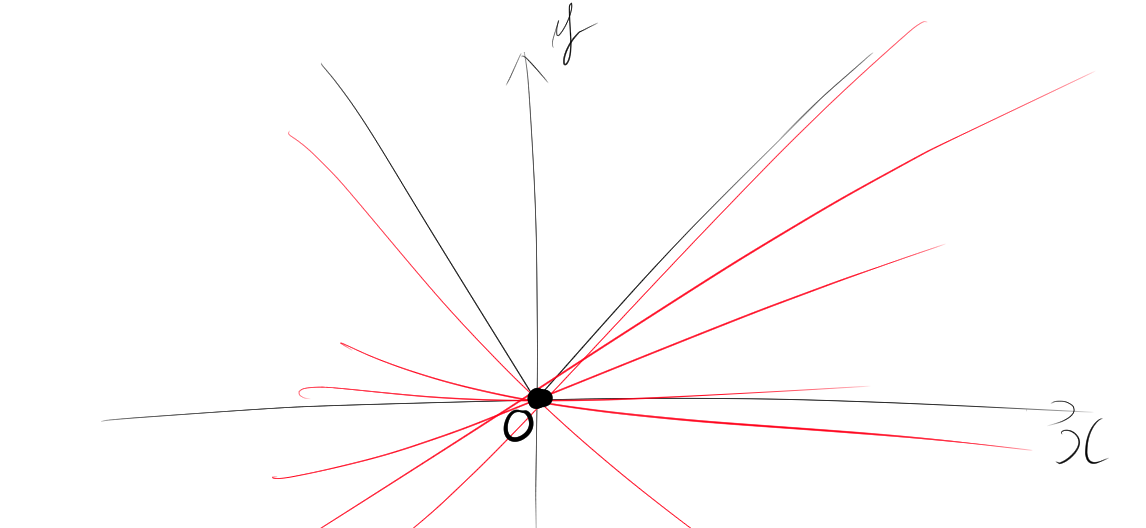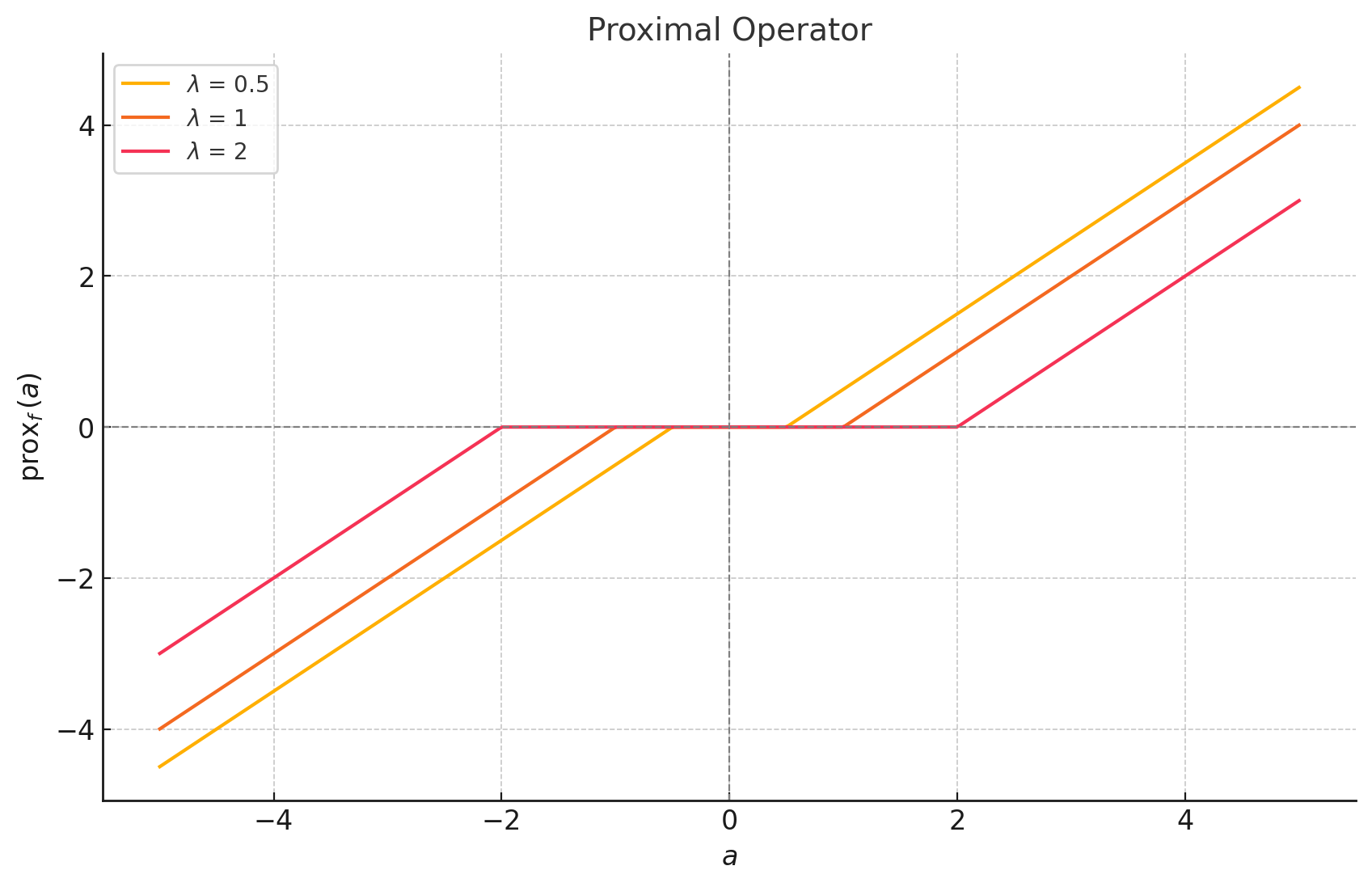近接写像の意味、微分と計算例について

- 1. 近接写像とは?
- 1.1. 別の記法
- 2. $f(x)=\lambda|x|$ の近接写像
- 2.1. (i) $x>0$ の場合
- 2.2. (ii) $x<0$ の場合
- 2.3. (iii) $x=0$ 劣微分
- 3. コンパクトな書き方の意味
- 3.1. $\operatorname{sign}(a)$
- 3.2. $\max(|a| – \lambda,\; 0)$
- 3.3. 実際に成り立つか確認
- 3.3.1. ケース①:$\boldsymbol{a > \lambda}$
- 3.3.2. ケース②:$\boldsymbol{|a| \le \lambda}$(つまり $-\lambda \le a \le \lambda$)
- 3.3.3. ケース③:$\boldsymbol{a < -\lambda}$
1. 近接写像とは?
近接写像(Proximal Operator)はある微分ができない点を含む関数 $f(x)$ を小さくしつつ、基準点 $a$ から極端に離れない点を探す。数式で書くと
二乗距離 $\tfrac12\lVert x-a\rVert^2$ が「遠くへ行き過ぎない」罰則を与えています。argminで最小値を与えるxを求めます。
1.1. 別の記法
近接写像はいろいろな書き方をされますが、次のように書かれることもあります。
$$ \mathrm{prox}_f(a) = \min \left \{x \in \mathbb{R}^n \,\bigl|\, f(x)+\dfrac12\lVert x-a\rVert^2 \right\} $$
2. $f(x)=\lambda|x|$ の近接写像
$f(x)=\lambda|x|$ の近接写像を求めてみましょう。
$$ \operatorname{prox}_{f}(a) =\arg\min_{x\in\mathbb R} \Bigl\{\; \lambda|x|+\frac12(x-a)^2 \Bigr\}. $$
絶対値の区間分け
$$ |x|= \begin{cases} \;\;x & (x>0)\\ 0 & (x=0)\\ -\,x & (x<0) \end{cases} $$
したがって目的関数 $g(x)=\lambda|x|+\dfrac12(x-a)^2$ を 3 区間で分ける。
2.1. (i) $x>0$ の場合
$$ g(x)=\lambda x+\frac12(x-a)^2. $$
微分して 0 に置くと
$$ \lambda+(x-a)=0 \quad\Longrightarrow\quad x=a-\lambda. $$
この解が区間条件 $x>0$ を満たす ↔ $a>\lambda$。
2.2. (ii) $x<0$ の場合
$$ g(x)=\lambda(-x)+\frac12(x-a)^2 =-\,\lambda x+\frac12(x-a)^2. $$
微分して 0 に置くと
$$ -\lambda+(x-a)=0 \quad\Longrightarrow\quad x=a+\lambda. $$
区間条件 $x<0$ を満たす ↔ $a<-\lambda$。
2.3. (iii) $x=0$ 劣微分
関数 $f(x) = |x|$ は、点 $x = 0$ において微分可能ではない。したがって通常の勾配(導関数)を用いることができないため、代わりに劣勾配(subgradient)と呼ばれる概念を用いる。
劣勾配は凸関数に対して「その点での接線の傾きの全ての値の集合」を指し、記号 $\partial f(x)$ で表される。
この集合は一般には複数の値を含むため、最適性条件を記述する際に等号「=」ではなく、集合への所属を表す記号「$\in$」を用いる。
例えば、次のようなy=|x|の関数を考えたとする。その場合、$x=0$の点で微分ができない。
であるので、x=0の点では$[-1,1]$の範囲の傾きでいくらでも接線がとることができる。
では、今回の近接写像$\lambda|x|$の例を考えてみよう。
$$ \mathrm{prox}_f(a) = \arg\min_x \left\{ \lambda|x| + \frac{1}{2}(x – a)^2 \right\} $$
は以下のように記述される:
$$0 \in \lambda\,\partial|x| + (x – a)$$
ここで、特に $x = 0$ のとき $\partial |x| = [-1,1]$ であるため、
$$a\in[-\lambda,\lambda]$$
つまり、絶対値を使って
$$|a|\leq \lambda$$
結果をまとめると、
$$ \boxed{% \operatorname{prox}_f(a)= \begin{cases} a – \lambda & \text{if } a > \lambda \\[6pt] 0 & \text{if } |a| \le \lambda \\[6pt] a + \lambda & \text{if } a < -\lambda \end{cases}} $$
ここで注意したいことは、近接写像で求めるのはxであるということですね。
また、コンパクトな書き方をすると、
$$ \operatorname{prox}_f(a) =\operatorname{sign}(a)\; \max\!\left(|a|-\lambda,\;0\right) $$
とのように書くことができます。
今回の関数をプロットすると次のようになります。
3. コンパクトな書き方の意味
各項の意味を見ていきます。
3.1. $\operatorname{sign}(a)$
これは「符号関数(sign関数)」で、$a$ の符号だけを抽出します:
$$ \operatorname{sign}(a) = \begin{cases} +1 & \text{if } a > 0 \\ 0 & \text{if } a = 0 \\ -1 & \text{if } a < 0 \end{cases} $$
3.2. $\max(|a| – \lambda,\; 0)$
$a$ の絶対値から $\lambda$ を引いた値を計算
それが負になるときは 0 を採用 →「$\lambda$ 未満の小さい値は0に切り落とす(しきい値処理)」という意味になります。
3.3. 実際に成り立つか確認
$$ \operatorname{prox}_f(a) = \operatorname{sign}(a)\; \max\left(|a| – \lambda,\; 0\right) $$
この式が、場合分けした次の形と一致することを確かめます:
$$ \operatorname{prox}_f(a) = \begin{cases} a – \lambda & \text{if } a > \lambda \\[4pt] 0 & \text{if } |a| \le \lambda \\[4pt] a + \lambda & \text{if } a < -\lambda \end{cases} $$
3.3.1. ケース①:$\boldsymbol{a > \lambda}$
- $|a| = a$
- $|a| – \lambda = a – \lambda > 0$
- $\max(|a| – \lambda, 0) = a – \lambda$
- $\operatorname{sign}(a) = 1$
$$ \Rightarrow \operatorname{prox}_f(a) = 1 \cdot (a – \lambda) = a – \lambda $$
✅ 一致!
3.3.2. ケース②:$\boldsymbol{|a| \le \lambda}$(つまり $-\lambda \le a \le \lambda$)
- $|a| – \lambda \le 0$
- $\max(|a| – \lambda, 0) = 0$
- $\operatorname{sign}(a)$ は何であっても 0 倍されるので
$$ \Rightarrow \operatorname{prox}_f(a) = \operatorname{sign}(a) \cdot 0 = 0 $$
✅ 一致!
3.3.3. ケース③:$\boldsymbol{a < -\lambda}$
- $|a| = -a$
- $|a| – \lambda = -a – \lambda > 0$
- $\max(|a| – \lambda, 0) = -a – \lambda$
- $\operatorname{sign}(a) = -1$
$$ \Rightarrow \operatorname{prox}_f(a) = (-1) \cdot (-a – \lambda) = a + \lambda $$
✅ 一致!
→ よって、1行式は、3通りのケースすべてにおいて正しいといえます。